|
|
隅田川に架かる佃大橋ができるまでは、渡し船で行き来していた佃島。その渡し船の碑の近くに住吉神社はあります。
江戸時代、徳川家康によりこの地を賜った、かつての大阪・田蓑村の漁師たちが摂津の住吉神社から分祀し、創建したといわれ、海上の守り神・住吉神が祀られています。
【 住所 】: 東京都中央区佃1-1-1-14 |
|
 |
 |
|
|
|
|
1466年(文正元)に疫病鎮護の神として創建された都内有数の古い神社。
1929年(昭和4)に創建された社殿の正面左右の梁には昇り龍と降り龍の彫刻が施されています。戦時中、度重なる空襲から神社を守り、出征した氏子全員が無事に帰還したことから別名「強運の龍」と呼ばれ、強運厄除けの力が宿るといわれています。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋小網町16-23 |
|
 |
 |
|
|
|
|
水天宮が有馬藩邸に祀られていた頃、妊婦が古くなった鈴の緒(社殿の鈴を鳴らす紐)のお下がりを腹帯に使ったところ、非常に安産で無事に丈夫な赤ちゃんが生まれたそうです。このことが評判となり、現在も全国から安産祈願に訪れる人で後を絶えない人気の神社です。
水天宮では、戌の日に安産祈願を済ませた腹帯「鈴乃緒」を授けていただけます。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋蛎殻町2-4-1 |
|
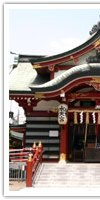 |
 |
|
|
|
|
かつて第六天神社と呼ばれていた榊神社は、日本武尊の際、鳥越の丘に国土創成の祖神を祀り、国家鎮護の神宮としたのがはじまりといわれる歴史ある神社です。
第六天神とは、祭神の天神第六代坐皇大御神(あまつかみむつのみよにあたりたまうすめおおかみ)を指し、諸業繁栄、健康長寿を授けてくださる神様として崇敬を集めています。
【 住所 】: 東京都台東区蔵前1-4-3 |
|
 |
 |
|
|
|
|
縁起によると、730年(天平2)に上野忍ヶ丘の地に創建された古社。940年(天慶3)には藤原秀郷が平将門追討の祈願に訪れたと伝えられています。
下谷神社の祭神の一人、大年神は食べ物、特に稲を司る神とされ、「稲が実を結ぶ」ことから円満和合のご利益があるとして信仰を集めています。
【 住所 】: 東京都台東区東上野3-29-8 |
|
 |
 |
|
|
|
|
平安前期の儒学者で歌人として知られる小野篁と、学問の神様で知られる菅原道真が祀られている神社。
諸芸に秀でた二神が祀られていることから、学問、芸能上達に大きなご利益があるとされ、多くの人々が参拝に訪れています。
【 住所 】: 東京都台東区下谷2-13-14 |
|
 |
 |
|
|
|
|
創建は定かではありませんが、日本武尊が東夷征伐の際、鷲神社に立ち寄り、天日鷲命に戦勝を祈願。凱旋した11月の酉の日に再び参詣し、戦勝のお礼に神前の松に熊手を奉納したとされるのが「酉の市」の由来とされています。
酉の市の”酉”を”取り”と解釈し、日本武尊が奉納したとされる熊手を福をかき込む道具に見立てて、酉の日に神社で熊手を手に入れると「福をかき込む」といわれています。
開拓、開運、商売繁盛の神様として信仰を集める天日鷲命が祀られている鷲神社です。
【 住所 】: 東京都台東区千束3-18-7 |
|
 |
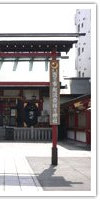 |
|
|
|
|
1063年(康平6)、源頼義、義家が奥州夷賊安倍貞任、宗任の征伐に赴く折、祈願のため京都の石清水八幡を勧請したのがはじまり。
今戸神社には、伊弉諾神と伊弉冉神という夫婦神が祀られていることから縁結びの神社として知られ、良縁を願って多くの方が訪れています。
【 住所 】: 東京都台東区今戸1-5-22 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|