|
|
宝田村の鎮守であり、もとは皇居前にあった宝田恵比寿神社。
祭壇中央に祀られている恵比寿像は、1606年(慶長11)に三伝馬取締役の馬込勧解由が徳川家康から譲り受けたものだそうです。運慶作とも、左甚五郎とも伝えられている恵比寿像です。
宝田恵比寿神社では、毎年10月19日、20日には盛大な「べったら市」が行なわれています。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋本町3-10-11 |
|
 |
 |
|
|
|
|
創建は一千年以上前、聖徳太子がはじめて市を立てた際、市の守護神として仰ぎ、商売繁盛、福徳の神と崇敬したことに始まるとされる古社です。
平安時代に藤原秀郷が平将門の乱を鎮定するために戦勝祈願したところされ、また室町中期にはひどい干ばつの折に江戸城の太田道灌が雨乞いのために山城国(京都府)伏見稲荷の五社の神、大己貴(大黒様のこと)を勧請して篤く信仰したと伝えられています。
江戸時代は恵比寿・大黒は一対という考え方があり、椙森神社には大黒様が祀られていたことから、椙森神社を深く信仰していた神道家の吉川惟足によって恵比寿大神が奉納されたといわれています。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋掘留町1-10-2 |
|
 |
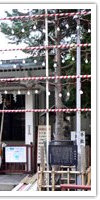 |
|
|
|
|
江戸時代、宇迦之御魂神をご祭神とする常陸の国(茨城県)の笠間稲荷神社の分霊を祀ったのが笠間稲荷神社です。五穀、水産、殖産の守護神として信仰されています。
笠間稲荷神社に祀られている寿老神は1976年(昭和51)に末社に祀られたもので、以後、日本橋七福神の一つとして信仰を集めています。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋浜町2-11-6 |
|
 |
 |
|
|
|
|
1596年(慶長元)に稲荷神社として鎮座し、吉原(当時は葭原と呼ばれていました。現在の日本橋人形町周辺)の氏神として信仰されてきた神社。
1675年(延宝3)の社殿修復の際、本殿から末廣扇が出てきたことから「末廣神社」と呼ばれるようになったそうです。
末廣神社には戦闘の神、勇気を与える福神として知られる毘沙門天が祀られています。毘沙門天の霊力により、多くの福徳、特に勝負運が強くなるといわれています。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋人形町2-25-20 |
|
 |
 |
|
|
|
|
昔、人形町周辺がまだ入り海だった頃、松の木がうっそうと生い茂る小島に祀られていたことから当初は「松島稲荷大明神」と呼ばれており、1916年(大正5)に「松島神社」に改称されました。
松島神社の祭神は14柱。
正徳の時代、この周辺を埋め立てて武家屋敷を造営するために、日本各地から様々な技術を持つ人々が集められ、居が構えられました。その際、街の中心にあったこの神社に、それぞれの故郷の神々が合祀され、たくさんの神様が祀られるようになったのだそうです。
大国神もそれらの神々の一つとして、正面の社殿に合祀されています。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋人形町2-15-2 |
|
 |
 |
|
|
|
|
安産、子授けで有名な水天宮。
その水天宮の境内に祀られている中央弁財天は、もと有馬家の下屋敷に祀られていたもの。
9代藩主・有馬頼徳公はこれを深く信仰しており、加賀百万石の前田公と能の芸を競うことになった際、この弁財天に願を掛け、勝利をおさめたと伝えられています。
学芸、財福、芸事の霊験あらたかとされ、信仰を集めている弁財天。毎年5日と巳の日に扉が開き、拝観することができます。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋蛎殻町2-4-1 |
|
 |
 |
|
|
|
|
昔、下総佐倉(現在の千葉県佐倉市)の城主、堀田家の守護神として祀られていたもの。この神社を祀って以来、屋敷はもちろんのこと、町方にも火災が起こらなかったことから、「火伏せの神様」と呼ばれ崇敬を集めています。
茶ノ木神社に祀られている布袋尊は、1985年(昭和60)に合祀され、日本橋七福神に加わりました。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋人形町1-12-10 |
|
 |
 |
|
|
|
|
1466年(文正元)に稲荷大神、倉稲魂命を主祭神として創建された都内有数の古い神社。配神として福禄寿と弁財天が祀られています。
1868年(明治元)の神仏分離令の際、安置されていた観音さまは別のお寺に移されましたが、七福神の福禄寿と弁財天はそのまま祀られました。しかし国家神道の時代なので、弁財天は市杵島姫命として、福禄寿は密かに祀られ、公にお祀りされるようになったのは戦後になってからだそうです。
【 住所 】: 東京都中央区日本橋小網町16-23 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|